
リプレイスとは?意味や具体的な作業内容などをわかりやすく解説
- ソフトウェア開発
- 2025年10月9日
システム老朽化への対応やDX推進など、様々な理由から既存システムの刷新は避けて通れない課題です。
しかし、リプレイスはコストも時間もかかる一大プロジェクトであり、「何から手を付ければよいのかわからない」「そもそもリプレイスとはどういったもの?」といった不安や疑問を抱えている方もいらっしゃるかもしれません。
そこで本記事では、リプレイスを検討および推進される企業の担当者様に向けて、リプレイスの具体的な定義からわかりやすくお伝えします。
さらに、リプレイスの目的や成功させるための具体的な手順や注意点なども解説するので、ぜひお読みください。
私たち一般社団法人日本ニアショア開発推進機構(ニアショア機構)は、首都圏を中心とした発注企業と地方にあるシステムリプレイスのできる開発会社をつなげる「Teleworks」を運営しています。
低単価ながら高品質のシステムをこれまで数多く提供してきました。テレワーク普及に伴い累計受注額は増加しており、相談実績は500件以上です。
このような実績がある私たちだからこそ知る、現場のリアルな声も紹介します。
なお、海外ではなく国内の地方で安全にシステムのリプレイスをしたい企業様は、私たちニアショア機構が提供する「Teleworks」の詳細をご確認ください。
IT分野における「リプレイス」とは?

IT分野におけるリプレイスとは、主に既存の情報システムやその構成要素(ハードウェア、ソフトウェアなど)を、新しいものに入れ替えることを指します。
単なる部分的な修正やアップデートに留まらず、システム全体、あるいは基幹部分を刷新する大規模なプロジェクトとなることが多いのが特徴です。
システム更改との違い
システム更改は、一般的に「システムを新しくすること」全般を指す広い言葉です。
システムリプレイスは、更改の一種であり、特に既存システムをまったく新しいシステムに入れ替えるニュアンスが強いと言えます。
一方、システム更改には、リプレイスのほか、既存システムを使い続けながら改修および機能追加をおこなうケースが含まれることもあります。
リプレイスは「丸ごと入れ替え」、更改は「新しくする」というイメージで捉えるとわかりやすいでしょう。
ただし、内容が同じ部分もあるため、「今後のシステム更新で〇〇のリプレイスをおこなう」という言い方をすることもあります。
マイグレーションとの違い
マイグレーションは、「移住」「移行」といった意味を持つ言葉で、IT分野では主に既存のシステムやデータを、構成を変えずに新しい環境へ移すことを指します。
例えば、オンプレミスのシステムをそのままクラウド環境へ移行する、データベースを別の製品に移し替えるといったケースがマイグレーションにあたります。
リプレイスが「システムそのものを新しいものに置き換える」のに対し、マイグレーションは「稼働環境やバージョンを移す」という点が主な違いです。
ただし、リプレイスに伴ってデータや一部機能を新しいシステムへ「移行」する作業が含まれるため、リプレイスの一部としてマイグレーションがおこなわれることもあります。
リプレイスの目的と背景
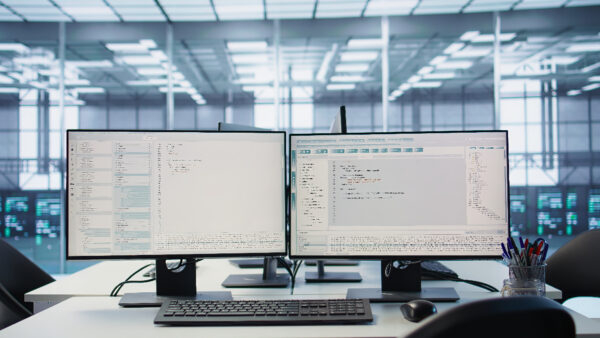
システムリプレイスは、単に古いものを新しいものに変えることだけが目的ではありません。
多くの企業がリプレイスに踏み切るのには、様々な切実な理由と、それを達成することで得られるメリットがあります。リプレイスの必要性をお伝えします。
新しい機能や技術の導入による業務効率化や競争力強化
事業部門からの要求として業務効率化や競争力強化が強い動機として挙げられます。
既存システムでは実現できなかった新しい機能や、クラウド、AI、IoTといった最新技術を活用したシステムにリプレイスします。
その結果、抜本的な業務プロセスの改善や新しいサービス開発を促進し、企業の競争力強化につなげることが可能です。
セキュリティリスクの低減とコンプライアンス強化
やむを得ないものとして、システムの老朽化や陳腐化への対応があります。具体的には、業種や法律の対応によるセキュリティ対応とコンプライアンス強化など。
古いシステムは、最新のセキュリティ脅威への対応が不十分であったり、OSやソフトウェアのサポート終了により脆弱性が放置された状態になりがちです。
リプレイスによって最新のセキュリティ対策が施されたシステムを導入することで、情報漏洩やサイバー攻撃のリスクを大幅に低減し、コンプライアンス要件を満たすことが可能になります。
システムの老朽化や陳腐化への対応
長期間利用しているシステムは、ハードウェアの劣化による故障リスクの増加を引き起こしかねません。
さらに、OSやミドルウェアのサポート終了によるセキュリティリスクの上昇、保守部品の供給停止など、様々な問題を引き起こします。
リプレイスは、これらの老朽化に伴うリスクを回避し、システムの安定稼働を維持するために不可欠です。
パフォーマンスの低下や処理能力の限界解消
企業の成長に伴う事業規模の拡大や、取り扱うデータ量の爆発的な増加により引き起こされる問題も考慮しなければいけません。
既存システムの処理速度が著しく遅くなったり、現在の業務要件を満たせなくなったりすることがあります。
システムのパフォーマンス低下は、従業員の生産性を下げるだけでなく、顧客サービスの質の低下にも直結しかねません。
最新の高性能なハードウェアやアーキテクチャで構築された新しいシステムにリプレイスすることで、処理能力を抜本的に向上させ、業務効率や顧客体験を改善できます。
システムのブラックボックス化や属人化の解消
長年の運用の中で度重なる改修を繰り返したり、開発に携わった担当者が退職してしまったりすることで、ブラックボックス化が起きることが少なくありません。
ブラックボックス化とは、システムの内部構造や詳細な仕様が誰にもわからなくなる状況のことです。
また、特定の担当者しかシステムを扱えない属人化が進むことがあります。
このような状況は、障害発生時の原因究明を困難にし、新たな改修を妨げるなど、保守・運用コストの増大を招きます。
リプレイスを機にシステムを再構築し、ドキュメントを整理および標準化することで、これらの課題を解消し、持続可能な運用・保守体制を築くことができます。
リプレイスの具体的な作業内容や進め方
リプレイスは、企画から導入、そして運用開始に至るまで、多岐にわたる作業と段階を経て進行する大規模なプロジェクトです。
ここでは、リプレイスプロジェクトの典型的な進め方をお伝えします。
- 企画・準備段階(目的・要件定義、方式選定、計画策定、ベンダー選定)
- 設計・開発段階(新システムの設計、開発・カスタマイズ、データ移行設計)
- テスト段階(単体テスト、結合テスト、総合テストなど)
- 移行・導入段階(データ移行、システム切り替え、ユーザー展開)
- 運用・保守段階(稼働後監視、不具合対応、改善、保守契約)
詳しくは、「システムリプレイスの進め方とは?よくある失敗パターンの回避策も解説」にて詳しく解説しているため、そちらをご覧ください。
リプレイスを成功させるための重要なポイントや注意点

リプレイスは多くの企業で失敗事例も少なくない難易度の高いプロジェクトです。
特に大規模なシステムを持つ大手企業では、その影響範囲の大きさから、計画段階での小さな見落としがのちのち大きな問題に発展するリスクがあります。
成功確率を高めるために、重要なポイントや注意点を解説します。
リプレイスの目的や要件を明確にして関係者間の合意形成を徹底する
「なぜリプレイスが必要なのか」「新システムで何を実現したいのか」という目的を曖昧にしたまま進めることは避けましょう。
プロジェクトの途中で方向性がぶれたり、関係者の期待値がずれたりして、手戻りや納期遅延の原因となることがあります。
システム部門だけでなく、利用部門、経営層など、すべての関係者間で目的と要件について十分な議論をおこない、合意形成を図ることが不可欠です。
既存システムの現状を正確に把握する(ブラックボックス化の解消)
リプレイスによる変更の影響を正確に把握しておくと、リプレイスの成功確率が格段に上がります。
例えば、既存システムがブラックボックス化している場合、新システムへの移行対象となる機能やデータの正確な把握が困難になり、設計ミスやデータ移行の失敗につながるリスクが高まります。
リプレイス着手前に、既存システムの仕様書やドキュメントを可能な限り整備し、システム内部の状況を把握するための調査を十分におこないましょう。
データ移行計画は綿密な策定とリハーサルを実施する
データ移行は、リプレイス作業の中でも特に専門性が高く、リスクの大きい工程の一つです。
- 移行対象となるデータの選定
- 新旧システム間でのデータ式の変換
- データのクレンジング(重複や誤りの修正・整形)
- 移行ツールの選定
- 移行のタイムスケジュール
- エラー発生時の対応手順
上記のようなあらゆる事態を想定した綿密な計画を立てる必要があります。
そして、計画倒れにならないよう、本番の移行作業前に複数回のリハーサルを実施しましょう。
移行にかかる時間や潜在的な問題を洗い出し、対策を講じておくことが極めて重要です。
十分なテスト期間と網羅的なテストケースを準備する
新システムの品質を確保し、本番稼働後のトラブルを未然に防ぐためには、十分なテスト期間を確保することが大切です。
実際のビジネスプロセス全体をカバーする網羅的なテストケースを準備しましょう。
特に、既存の他システムとの連携部分や、通常は発生しないようなイレギュラーなケースを想定したテストは入念におこなう必要があります。
テストで発見された不具合は確実に修正し、リリース判定の基準となる品質目標をクリアしていることを確認してから、次の工程へ進むという規律を守ることが大切です。
スケジュールと予算に無理はないか確認する
リプレイスプロジェクトは、予期せぬ技術的な問題や仕様の考慮漏れなどが発生しやすく、計画通りに進まないことが少なくありません。
あまりにタイトすぎるスケジュールや、必要最低限ギリギリの予算で計画を立ててしまうと、問題が発生した際に柔軟な対応ができないことも。
そういった状況は、かえって大きな遅延や追加コストを招くリスクが高まります。
計画段階で、起こりうるリスクを想定し、適切なバッファ(予備期間や予備費)をあらかじめ見込んでおきましょう。
これが、プロジェクトを安定的に推進する上で重要です。
協力体制を築ける信頼できるベンダーを選定する
リプレイスの多くの工程は外部ベンダーに委託することになります。
ベンダーの技術力や実績はもちろん重要です。しかし、それ以上に、自社の状況を深く理解し、親身になって課題解決を提案してくれるかがリプレイスを成功するためのポイントになります。
円滑なコミュニケーションが取れるかといった良好なパートナーシップを築けるかどうかが成功を左右します。
外部ベンダーは、複数の候補から慎重に選定してください。
例えば、私たち「ニアショア機構」が運営する「Teleworks」では、大手企業様のリプレイスにおける外部パートナー選びを支援しています。
首都圏をはじめとする発注企業様と、地方に拠点を置く高品質なニアショア開発会社様をおつなぎしております。
システム開発会社と直接契約することで中間マージンを抑えつつ、顔の見える関係での開発を実現可能です。
Teleworksに登録しているのは、テレワーク開発に必要な知見を身につける独自の教育プログラムを修了した8,000名以上の正社員エンジニアです。
高い技術力と安定した開発体制を提供可能で、小規模なリプレイスや特定機能の刷新からでもスタートできます。
相談実績500件以上といった豊富な実績に加え、長崎新聞や南日本新聞など多数のメディアで紹介されるなど、高い信頼性を誇っています。
リプレイスの外部委託をご検討の際は、ぜひニアショア開発という選択肢も視野に入れてみてください。
変更管理と社内外のコミュニケーションを徹底する
リプレイスプロジェクト中に要件や仕様の変更が必要になる場合、その影響範囲を正確に評価しましょう。
そして、関係者全員に周知および合意を得るための変更管理プロセスを明確に定めておくことが重要です。
また、プロジェクトの進捗状況、課題、決定事項などを定期的に社内外の関係者に報告や共有をおこない、密なコミュニケーションを心がけましょう。
ユーザーへの十分な周知とトレーニングをおこなう
新システムは、実際に利用するユーザーにとって使いやすいものでなければ、導入の効果は半減してしまいます。
リプレイスの早い段階からユーザー部門を巻き込み、フィードバックを設計に反映させることが望ましいでしょう。
また、システム稼働前に、ユーザーへの十分な周知期間を設け、操作方法や変更点のトレーニングを実施することで、円滑な移行と早期の定着を促進できます。
稼働後のフォローアップと継続的な改善計画をおこなう
システムをリリースして終わりではなく、稼働後に実際に利用する中で発生する不具合や改善要望に迅速に対応する体制を構築することが重要です。
また、新しいシステムを最大限に活用するために、定期的に利用状況を分析してください。さらに、継続的な改善計画を立てて実行することで、リプレイスの投資効果を最大化できます。
リプレイスをするならニアショア機構へ
システムリプレイスは、企業の成長や競争力維持のために避けては通れない重要な経営課題です。
言葉の定義を正しく理解し、なぜリプレイスが必要なのかという目的を明確にした上で、体系的なプロセスに基づき、計画的かつ慎重に進めることが成功のポイントとなります。
特に大手企業におけるリプレイスは影響範囲が大きく、多くのリスクを伴います。しかし、本記事でお伝えしたような重要なポイントや注意点を押さえると成功の確率が高まります。
また、適切な体制を整えながら、信頼できるパートナーと共に取り組むことで、そのリスクを低減し、成功へと導くことが可能です。
リプレイスを検討される中で、外部の専門家の知見やリソースを活用されたい場合は、私たちニアショア機構の「Teleworks」にご相談ください。
高品質なニアショア開発会社とのマッチングを通じて、企業様のリプレイスを力強くサポートいたします。
著者:
金融、ITベンチャーを経て株式会社パソナ(現)にて事業企画・実行に従事。大規模法人向け外注戦略を担うコンサルティング部門を企画設立し部門長。その後、IT調達分野のコンサルティング会社を設立し、セミナー・寄稿多数。外注戦略支援、コスト最適化、偽装請負是正では国内有数の実績を持ち、システム開発会社の再構築・再生も多数実行。2013年より「ニアショア活用による地方活性化で日本を再生する」ビジョンのもと、一般社団法人日本ニアショア開発推進機構を開始。
